内藤誠、『番格ロック』を語る vol.2

第1部
1-1
ヌーヴェルヴァーグの季節に撮影所へ入る
──東映の撮影所に入られたときの雰囲気っていうのはどういう感じがしましたか。
内藤:あれは、1959年。うん昭和34年の4月からだった。とにかく、京都はこわいっていうふうには思ってたね。まぁ時代劇はあんまり性に合わないと思ってた。どうせフィクションだったら、ああいうのは自分の体質に合わないっていうか、まぁ当時の東映のチャンバラはよく見たけど、明けても暮れても撮るのは自分にはちょっとしんどいっていうのがあったから、京都へ行くのはちょっとね嫌だっていうぐらいのことはね思ってました。希望出すわけだからさ、だからそれはきちんと言ったと思う。で、日活にも願書出してたからね、まぁ受験までしなかったけど。先に東映に決まっちゃったから。だからもし東映で京都撮影所へ行くっていうのが条件だったら、たぶん日活を受けていたと思うんですよね。日活は事務系と現場とをね、試験の段階で区別しなかったんですよ。だから東映は区別してたから必ず現場人間になれるっていうのはわかってたから。だからまぁそういうことがあって、日活は学内選考は通ってたけど行かなかった。
──1958年が日本映画の観客動員数最高の年ですから、1959年といえば、その翌年ということで製作本数が一番か二番くらいに非常に多かった年ですよね。
内藤:うん、多かった。いつまで助監督やるんだろうなぁと最初思ったんだけど、第二東映とかニュー東映ができたおかげで、先輩がみんな監督になっていっちゃってね。上がいなくなっちゃった。セカンドになってチーフになってって、テンポアップされるじゃないですか。だから僕らのころまでは、みんな8年くらいで監督になってるんだよ。で、まぁ辞めちゃった人とか、所長になったりとかね、いろんな職替えをした人がいるんだけど、とにかく上がいなくなっちゃった。そこは松竹なんかと違うんだ。
──監督が著書でよく言及される1959年に製作されたゴダールの『勝手にしやがれ』を観られたのはちょうどその頃でしょうか。
内藤:僕らが見たのは60年だよ。そりゃビックリしたね、やっぱり。ちょうど覚える頃じゃないですか、東映の撮影所で映画の撮り方を。カットバックとか、そうやって撮るのかって。だけど、同じポジションで繋いだりね、ああいうの平気でやっているでしょう。例えばジャンプカットの問題だってね、まぁ理論的にはすぐ辿り着いたかもしれないけどね。同じポジションで物凄く時間が経ったって別にいいじゃないっていうのはね。だけど、やっぱりゴダールの映画では具体的にやっているのを見ちゃったからね。ああこれでいいんだっていうね。
──東映の助監督時代、ゴダールについては監督の周囲でも話題になっていたのでしょうか。
内藤:なりました。例えば、少なくとも野田(幸男)さんは、やっぱり興奮して喋っていました。過去の作品とは、やっぱり質が決定的に違うからね。自分が監督になって、現場でどうのこうのしよう、っていうのはなかったけどね。だけど……うん、「これが映画だ」とは思いましたね。あの頃のゴダールは本当に凄いっていうかね、『気狂いピエロ』(1965)とか感動しましたね。あの頃観た映画っていうのは、戦前の名作をいっぱい人生坐で観る、っていう、そういう時代だからね。漠然とフランス映画とかアメリカ映画とかのいわゆる名作路線っていうのは観ているんだけどねえ。もっと根源的に凄い人たちがいるって思いましたよ。
それ以前にも学生時代、映画がここまでやれるんだっていうのは、ロベール・ブレッソンの『抵抗』(1956)っていうのを観てね、決定的に「映画は凄い」って思いましたけどね。映画の現場を本当にやりたい、っていう風に。川島雄三が好きだ、とかそういうのとはまた別にね。密室から逃げ出すだけの話なんだけれども……なんていうのかな、文学とはちょっと違うね……レジスタンス運動をやっているフランソワ・ルテリエを主人公に使って、あれだけ緻密にものを作るっていうのは、あの当時の現代文学だってここまではやらないなあっていうか、それくらい吃驚しました。それが丁度、助監督試験を受ける頃だったから、「ここまでやる奴がいるから映画って凄いなあ」って思ったんですよね。
ゴダール以前にブレッソンなんかを観て、どうせ自分がこれから進めるのは、娯楽映画ばっかり撮る会社ではあるけれども、映画は基本的にはこういうことができるっていうことを考えました。だから、東映のプログラムピクチュアを撮った後に自主映画をやる時は、初心に還るっていうかね、アナーキーなことも平気でやるっていうかね……もっとやりたいと思っているうちに映画がなかなか撮れなくなっちゃって、今も準備中(笑)。
──上の世代の監督の方々がゴダールについて語られたりはしていませんでしたか。日本の撮影所では、あの型破りなスタイルを否定的に語る前世代の監督はいらっしゃらなかったのでしょうか。
内藤:観ているには違いないとは思うけれども、まあ、あんまり上の世代の監督とゴダールの話をした記憶はないですね。悪口はいっぱい聞きましたけどねえ(笑)。でもそれはストーリーテリングがない、とかごく普通の悪口だから、まあ、聞いてもしょうがないっていうね。
でも、日本だって戦前からそういう映画はあったんでしょ。清水宏の『有がたうさん』(1936)なんか、オールロケーションで。ちゃんとやることやってるじゃあないか、っていうね。
ヌーヴェルヴァーグにはフランスの人たちは、ぼくらほど吃驚しなかったんじゃあないかな。ジュリアン・デュヴィヴィエ的なものを向こうの人たちは必死になって拒否したんだろうなあ。ジャン・ギャバンの初期の作品とか、『地獄の高速道路(ハイウェイ)』(1955)とか観たら、ヌーヴェルヴァーグと割と繋がっているんじゃあないの。
──一方、ゴダールの日本公開に先立つ1957年の作品『愛と希望の街』を嚆矢として、松竹ヌーヴェルバーグと後に読売新聞記者だった長部日出雄によって総称された、新しい世代の新人監督たちの作品が登場した頃だと思うのですが、新しく映画の世界に入る若者としてそうした動きをどのようにご覧になっていましたか。
内藤:松竹に非常に新しいひとたちが出てきた、と思ったね。吉田喜重の『ろくでなし』(1960)とか、東映の助監督としては追っかけて観てたけどね。でも松竹ヌーヴェルヴァーグっていうのはジャーナリズムが付けた呼称であってね、松竹の新人たちっていう感じでしたかねえ。たしかに、新しい時代が来たっていう感じがした。俺たちも早くそうならないかなあって思ったことは事実だね。
早くヌーヴェルヴァーグみたいなのが東映でも出てきて、日ごろ俺たちのやっているルーティンワークをみんなひっくり返しちゃえばいいのにと。若い助監督たちは誰もが思ったんじゃないですかね。わざわざ口に出さなくっても、気分としてみんな思ってたんじゃないですかね。
──彼らの特徴は戦後に撮影所に入ったはじめの世代だとという点にあります。ほかにも大映の増村保造や東宝の須川栄三、日活の中平康などが登場しましたが彼らの活動はどう思われましたか。
内藤:確かに中平康が『狂った果実』(1956)を撮って、それをフランスの連中が観てヌーヴェルヴァーグを作ったっていうけど、そして中平さん自身がヌーヴェルヴァーグは自分の後輩だっていうけど、あれを観て、これがヌーヴェルヴァーグだとは思わなかったよね。普通に新しい映画だという感じ。ぼくらの個人史として中平映画は、新しくて面白かったけど、『勝手にしやがれ』ほどの衝撃は受けなかった。
──松竹やフランスのヌーヴェルヴァーグの反抗、といいますと内藤さんたちも、今井正監督の作品などそれまでの東映のある種の傾向に反抗しよう、というような感じはありませんでしたか。たとえば、『不良番長』(1968)の中で鈴木やすしが飛行場の手すりを監獄の鉄格子に見立てて「まだ最高裁がある!」と、今井正監督の作品『真昼の暗黒』(1956)のパロディを演じる一景がありますが。
内藤:いや、あれはパロディにもなってないよね(笑)。ちょっとふざけただけで。ただ、何でもおかしくして、アナーキーに笑っちゃおうっていうのがあったんです。それから、ぼくとか山城(新伍)や梅宮(辰夫)なんかはもう、今井正監督や家城巳代治監督みたいなリアリズムはできない、というのがあった。
──内藤監督と同じ1936年生まれの批評家・蓮實重彦の著書『映画の神話学』に「ゴダールに熱い興奮を禁じえないひとつの魂が同時にマキノ雅弘にも涙してしまうという現実……」で始まる有名なフレーズがありますが、内藤さんは助監督時代にゴダールに憧憬されながらも、実際にマキノ雅弘監督の現場におつきになられていたそうですね。どのような現場でしたか。
内藤:うん、マキノさんのチーフは2本くらいやっています。澤井(信一郎)君という優秀な助監督がいるから、ぼくは遊んでいたようなもんだけど、忙しいからB班をたてなくてはいけないという時は、もう緊張して撮っていた。あとはマキノさんの、お話をアハハと笑って聞いているっていう、それだけでね。具体的にびしっとした仕事は澤井君が全部やってくれてたから。彼はもうマキノ門下だからね。東映の場合、助監督のシステムは順番制みたいなものだから、まぁ僕はつくわけだけれども、仕切りは優秀なのがついているから。遊んでました(笑)。
──その時、マキノ監督はどんな話をされていたんですか。
内藤:いやもうとにかくマキノさんの著作の『映画渡世』みたいな、ああいう話ですよ。だから、どこまで本当かなぁって。面白すぎるからね。映画史的に正しいかどうかなんて思う以前に笑ってるんだけどさ(笑)。僕は順番制で、たまにマキノさんにつくから、全部おかしいじゃない? だけど澤井君なんかはもう何本もやってるから、「またか」って感じがあるんだろうけど、僕は心の底から笑っちゃうからね。先生としてはこんないい聞き手役いないっていう(笑)。質問だって、はじめて聞くからちゃんとするじゃない? だからね、まぁそういう点ではよかったんじゃないかなあ(笑)。
だから監督にいよいよなるっていうときには、「あいつはいいよ。デビューさせてやれ」って言ってくださったらしい。でも、現場で何やってたかっていったら、働かないで先生の話を聞いてる(笑)。だって、みんなセットで働いてるのにさぁ、僕はスタッフルームで先生の話を聞いて、笑ってるだけ(笑)。B班撮影のときは、仕方がないから、緊張して撮りましたけども。
──たとえば、マキノ監督の『昭和残侠伝 唐獅子仁義』(1969)の冒頭などは内藤監督が撮られたそうですが。
内藤:うん、本流の芝居に関係しないとことかはね。それから、たとえば主題歌が流れて健さんが殴りこむところ。一番は先生が撮る。それから二番は僕です。タッチは全然マキノ調ではないけどさ(笑)。それなりに一生懸命に全カット自分でも絵コンテ書いてました。自分の作品だってコンテ書いたことないのに。マキノさんのB班につく以上は、さすがに自分でコンテ書いて、スタッフにこういう風に撮りたいって。マキノさんだと、さーっと健さんが歩いているだけなんだよ。どうたらこうたらって、巨匠は考えないようなことを、僕はなんか面白くしたいと思っていろいろやってね。で、編集して観たら、B班はオーバーで大袈裟ったらありゃしなくてね。だから僕がB班で撮るときは、マキノさんに画調を合わせようと思って、芝居を撮るときは2台使ったけど、出だしとかね、そういうとこはどうしても1キャメラで狙って撮りたいっていう風になっちゃう。2台だと撮れないんだよ。いい画っていうのを、どうしても考えてしまう。もうひとつのキャメラが邪魔になっちゃうでしょ。そういう発想だからね。でも、マキノさんは芝居中心だからね。ハリウッドみたいに、2台のキャメラで撮るんだよ。
──他に助監督時代には、カルトムーヴィーの誉れ高いミュージカル映画『乾杯!ごきげん野郎』(1961)をはじめとして瀬川昌治監督の作品につかれていますね。
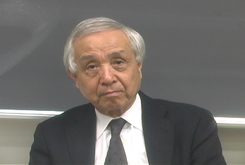
──撮影が終わった後にセッションがはじまっちゃったって、瀬川さんがおっしゃられていました。
内藤:そうですね。ジャズやっている俳優さんたちが出ていたからね。南廣のドラムスはフランキー堺と双璧をなすくらい。台詞はトチってもドラムはね。それに世志凡太のベースも一流だったから。この前、久しぶりに世志凡太さん会いましたよ。南廣は亡くなっちゃったけど。彼らが、撮影は終わったのにトニー・スコットに合わせて演奏しちゃってね。
──内藤さんが助監督として関わられた作品の中で、溝口健二監督の内弟子をされていて、『赤線地帯』(1956)をはじめ伊藤大輔、内田吐夢、豊田四郎、加藤泰などの名脚本家であった成沢昌茂監督の作品についても非常に興味があります。内藤さんはすでに「わが師についてのメモ」という名エッセイを書かれていて、一読すると非常に魅力的な像を結びます。どのような演出をされていましたか。
内藤:自分で動くんではなくて、役者の耳元でぼそぼそやってました。自分のイメージにはめようと、僕らはどんどん進めちゃうんだけれども、成沢さんの場合は、自分のイメージにたどりつくまで根気よく待つんです。あんまりモンタージュを気にしない。同じ東映でも与えられる素材がわれわれとぜんぜん違うから、一概に比較はできないけれども、まあ、やり方が違うんだね。『雪夫人繪圖』(1975)のときは、雪婦人の歩いた跡だっていうことで、冷たい雪の中を足跡を点々とつける撮影がありました。溝口流のリアリズムで実際の人間の足跡じゃなきゃいけないっていうことになった。本当にリアリズムだったら雪婦人の佐久間良子さんが足跡つけなきゃいけないはずなんだけどとボヤキながら、B班監督の僕がはだしで雪の上を歩きました(笑)。
──最近は『二匹の牝犬』(1964)くらいしかリバイバル上映されることのない渡辺祐介監督はどのような方でしたか。
内藤:ひたすら真面目な人でねえ、一生懸命喜劇をやろうとするし、デビュー作の『少女妻 恐るべき十六才』(1960)というのがいい映画でねえ。ぼくら、大蔵貢の新東宝映画も面白いなんて平気で言っちゃうじゃない。そうすると、「何言ってるんだ!」って怒られたりして。大蔵貢体制を俺は許さないっていうところがあってね。瀬川さんの後輩なんだけどね。『九ちゃんの大当りさかさま仁義』(1963)なんか、九ちゃんとかジェリー藤尾とか歌った唄を僕が作詞したりしてたんだ。多作な監督で、何でも撮れちゃうからだろうね。彼ならできるだろうって信頼されているんだ。
1-2
未映画化脚本について
──内藤監督は80年代に脚本家の桂千穂とのコンビで多くの脚本を執筆されますが、助監督時代には、のちに『不良番長』シリーズを一緒に撮ることになる野田幸男監督らとシナリオ集を出していたそうですね。
内藤:脚本集を作るくらいしか憂さ晴らしもないし、出せば必ず企画部に持って行きましたけどね。
自分が映画を作るようになってから、台詞とか、この中のワンシーンを使っちゃえとか、そういうことはしてたけど、遂に自分が監督になるまで、その中のシナリオは1本も映画にならなかった(笑)。
──どのような脚本を書いていたのですか。
内藤:『勝手にしやがれ』の影響で『とぼけて走れ』っていうのを書いたりね。ぼくが書くから起承転結があって、ストーリテリングしちゃうんだけど。アレン・ギンズバーグの詩なんかが出てきたりしてね。それを深作欣二監督が読んで、あれはなかなかいいからっていうんで『誇り高き挑戦』(1962)で使ったりね。まだ翻訳が出る前だからね。勝手に使っちゃって大丈夫ですか、って聞いたら、ギンズバーグがこの映画を観るわけはないっていうことで出しちゃった(笑)。学生時代にアメリカ文学研究会っていうのに入っていたし、助監督で欲求不満だから、紀伊國屋の洋書売り場に行って、まだ訳されてない本を見るという趣味があったんだけどね。『戦いの遠いこだま』っていうのも書いたんだけど、これは、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』がまだ翻訳が出ない頃に紀伊國屋で買って来て、易しい英語だから読んで、このストーリーテリングはいいなあ、と思って一級下の助監督だった館野彰、後に塙五郎っていうペンネームで名シナリオライターになる彼と、一緒にシナリオを書いた。フットボール選手の兄とその妹を主人公にしたハイティーンもの。妹とは仲がいいんだけど、学校とかいろいろなものへは嫌悪感を抱いて反抗してる兄の話。シチュエーションはもろサリンジャーなんだけど。いい台詞は使おうっていうことで、台詞もそのまま和訳しちゃって、もろパクリでシナリオを書いちゃった(笑)。あんなえらい作家とは知らなかったんだ。あとは、企画部長に渡したら脚本をなくされちゃったんだけど、清水一家が清水港で沈没した咸臨丸を引き上げて、これからは英語の時代だっていうんで、お寺で英語の塾を開いて、時あたかもアメリカのカルフォルニアで金鉱が発見されたから、清水一家がそれを手に入れに行くっていう喜劇。ビリィ・ザ・キッドが出てきたりして、これでデビューしようと書き上げたんだけど、スケールが大きすぎるっていうことで相手にしてもらえなかった(笑)。
──脚本ということでは、後に監督になられてから、脚本で関わられた深作欣二監督の『血染の代紋』(1970)は映画化されましたが、70年代には2本の重要な映画作家の未映画化脚本に関わられていますね。まず鈴木清順監督作品になる予定だった『母に捧げるバラード』についてお伺いしたいのですが。
内藤:海援隊の曲が元にあった企画でしたね。あの時、鈴木さんの意見で一番印象的だったのは、やっぱり吉原がみんなソープランドになっちゃうんだけど、一軒だけ逆らっている店がある、というのが舞台として面白いということ。それが東映で出来なくてね。だから、後にそのストーリーをほとんどいじらないで、荒戸源次郎製作で僕が『時の娘』(1980)という題名にして監督したんです。それで、もうひとつ、全然違う『母に捧げるバラード』のストーリーを書いたんですよね。それまで関わってくれていた佐々木守[脚本家]が忙しくなって、鈴木さんとふたりでシノプシスまで書いたんだ。やくざ映画に近いのにしていたと思うんだけど。まぁ最近読み直してないから覚えていない。あることはあるんです、もう1本ね。それをやっと書き上げた頃に、もう期限切れになっちゃった。それで解散しちゃったんだけどね。最初は山の上ホテルでやってて、格好よかったんだけどさぁ。2ヶ月くらいやってたような気がするなぁ。だんだん金なくなってきてさ、最後は僕のところでやっていたからね。僕と清順さんと膝つき合わせて、妻が料理を作って(笑)。
──続いて、最近『大島渚著作集』(現代思潮新社刊)に収められて一般でも読むことができるようになった大島渚が監督する予定だった『日本の黒幕』について教えてください。
内藤:同じ題名の映画が東映で降旗(康男)さんの監督で撮られる時に、電話がかかってきてね。「いいとこ使っていいな?」って。僕はもちろん好きなようになさっていいじゃないですかって言ってね。だから、随所に似たところはあるんだとは思いますけどね。
我々が書いてたやつは、『日本の首領』(1977-78)とか、東映のああいう伝統あるじゃないですか。それに近づけてやれば映画化できたかもしれない。でも、なんかねぇ。テロリストの少年に焦点を当てて、赤い靴の少女は川喜多和子のイメージを入れようなんてことをで言ってた(笑)。大島さんと一緒に京都の旅館でね。だけど、あれも期限切れだった。大島さんは、週に何日かテレビの『女の学校』とかの収録のために東京行っちゃうんだよ。この間も僕はやっていたんだけどね。うん、……もうひとり客観性のある人がついてた方がよかったかもしれないな。
1-3
幻のデビュー作
──内藤監督のデビュー作は『不良番長 送り狼』(1969)と一般的なプロフィールには書かれていますが、それ以前に東映製作のドキュメンタリー映画『これがベトナム戦争だ!』(1968)という作品を野田真吉さんと共同で演出をされているのですね。
内藤:やってますね。これは公開以来、見直してないんですけど、今でも見たいと思ってます。なんか機会があればと思うけど、ないんですね。イラク戦争が起きたとき、ひょっとしてやらないかなぁと思って、東映チャンネルのプログラムをよく見てたんだけど、やらなかったですね。社員の人が、そんな映画があることを忘れてるかもしれない。東映の公開年表を見れば、ちゃんと載っているはずですけどね。台本なんかは私が持ってます。
──あれは、シネマスコープサイズの東映の一般の映画と同時上映だったのでしょうか。
内藤:たしか村山新治監督の『あゝ予科練』(1968)の添えものだったと思いますけど。スタンダードのモノクロです。北ベトナムと南ベトナムのフィルムが手に入るルートがあって(笑)。まぁいかにも東映らしいんですけどね、それで、モンタージュして作ったんです。野田真吉さんが、政治的な立場で、タイトルを出すことができないっていう理由があってね。で、ふたりで共同でやってたんですけれども、野田さんのタイトル出すとフィルムを提供しないっていうことがあってね。で、僕もタイトルはなしで、ギャラだけいただきますっていうことで、共同演出ということにして。もう仕上げは僕だけで、途中から野田さんは作業できなくなっちゃたんだね。だけどコンセプトは一緒にやりましたから、共同演出ということになって。野田さんもそう書いてますよね。
──ニュースフィルムを素材として使った作品だったのでしょうか。
内藤:ほぼニュースフィルムで、もっぱら仕事は編集をふたりでしてたっていうことと、ナレーションを作ったていうこと。本当は、ふたりの名前をタイトルに出していいんだけれども、それが出せないから大宅壮一さんに監修してもらったんです。なかなかいいアイデアを出してくれましたよ。当時の少年マガジンでよくやってるように、武器の名称はスーパーインポーズして全部入れろとかね。そういうのが、なかなか面白くて、さすがだと思いましたけどね。僕も野田さんもああいうエンターテインメントの方向性はなかった(笑)。
──野田真吉さんは、どんな方でしたか?
内藤:ひたすら真面目な人だったね。それ以後もときどきお会いしました。あのときの経緯は『ある映画作家──フィルモグラフィ的自伝風な覚え書』(泰流社刊)に書いてあるとおりです。僕があの文章に異議をはさむことは全然ありません。あのとおりですね。彼はそういうキャリアで生きてきましたたから。ぼくの方はそのうち、『不良番長』シリーズのポジションだから、別になんの問題もなかった。音楽は、間宮芳生ですね。いい音楽だったと思います。だから間宮さんもね、監督たちがタイトル入れないんだったら、私も仕事だけして、タイトルは入れませんって言い出してね(笑)。間宮芳生の音楽なのに、彼のタイトルも入ってない。
うん、だからね、タイトルが入ってるのは、大宅壮一だけ(笑)。不思議な映画。だけど、東映で公開するのになんの問題もなかった。むしろ大宅壮一の名前があれば、いいってことだったから。もう大宅さんは最晩年だから、編集室に上がるのに僕の肩に掴まりながらで、ふたりでよくいろんなことを話しましたけどね。
──野田さんが抜けてから大宅壮一さんが入られてたのですか。おふたりが一緒に仕事をされたのでしょうか。
内藤:僕はまぁ大宅さんと一緒にダビングやったり編集の意見を聞いたりしてた記憶はありますけどね。大宅さんと野田さんはね、ひょっとしたら一緒に作業してなかったかなぁ。後半僕がひとりでやってたっていう記憶があるから。ただ嫌がってはいませんでしたよ。公開できることのほうがよかったし、ギャラも野田さんにちゃんと入るわけだし。僕は社員でしたから、どちらでもよかったんですけれども(笑)。
──台本は内藤さんがお書きになったんですか?
内藤:いやいや野田さんと一緒。野田さんの意見が十分に入った脚本です。僕はまだ新人というか、助監督みたいなもんですから。でもふたりで本当によく打ち合わせはしましたから、あの方が映画作ると僕を呼んでくれたりして、生きている間はよく付き合いました。ああいう真面目な人と付き合って、よかったと思いますけど(笑)。
(第2部に続く)
Warning: include(/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2009/07/2009-07-01_180000.php on line 189
Warning: include(/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2009/07/2009-07-01_180000.php on line 189
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.3/lib/php') in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2009/07/2009-07-01_180000.php on line 189
